黒沢明の名作「生きる」を原作として、同時代のイギリスを舞台とした映画「生きる LIVING」を観ました。ゴールデンウィークは映画館でいろいろ映画を観ようと思っていたのですが、観ることができたのはこの1作だけでした。ちょっと残念。GWの後半から観たいと思う話題作が公開されているので、大型連休が明けてから機会を見つけたいと思います。
さて本作ですが、公開を楽しみにしていた作品であり、本作に臨む前に原作の黒澤明の生きるも観かえしました。第2次世界大戦直後の日本、そしてイギリスの市井の人の物語を、なぜ今再び世界で共有するのか。その背景とそれによって変えられることとは何だろうかと。そんなことを考えながら、本作の背景・ストーリー・撮影と編集について整理しておきます。
生きる LIVING ―― 作品の背景について

2023年、目の前には片づけなければいけない課題・問題が山積みとなっていて、周囲を見渡すと自分の周囲の問題解決にファナティックになり、利己的な振舞いを続ける人や国がたくさんあります。そんな環境の中で、本作の主人公が死に際してとった行動。誰かのために、利他の気持ちで行動することの大切さと美しさが良くわかりました。きっとだから今、この作品が再び制作されたのだと思います。本作でも描かれていたように、利他的な行動はすぐに多くの人に賞賛されるものではありません。しかし、一部の人の心には深く残り、ゆっくりとでも確実に、次の世代に語り継がれる行動となるのです。目の前の出来事に躍起になり、次の次の世代のことにまで想像を膨らませることができない状態の我々に、そのことを伝える映画であったとともに、70年を経て、再び映画化される物語としてそのものを体現してくれた映画でした。
生きる LIVING ―― 作品のストーリーについて

本作のナラティブは、公務員の「ウィリアムズ」。しかし、彼は物語の中盤で胃がんでなくなり、そこからナラティブを紡ぐのは生前の彼と仕事をともにしてきた同僚たち。そして、死の間際に彼を目撃した警察官です。黒澤作品と同じストーリーです。そして、このナラティブの移行が本作が名作たる理由だと分かりました。
主人公は永年公務員として勤め、欠勤することさえないまじめな仕事人ではあるけれど、目の前の仕事を効率的にこなすことを優先し、融通が利かない公務員でした。しかし、そんな彼は医師に胃がんで余命僅かだと宣告されます。愛する息子にさえもその事実を伝えることができず、一人で抱え込む主人公。まじめに勤めることだけが自分の人生だったのかと疑問に思い、仕事を休み、夜の街に出て享楽的に遊んでみたけれどしっくりとこない。そんな時に、公務員を辞めることを決意した、部下の「マーガレット」と街で出会います。彼女の奔放な性格に憧れを抱き、ウィリアムズはマーガレットと同じ時を過ごしたいと彼女と一緒に過ごす時間を作り続けます。しかし、新たな仕事・環境を経たマーガレットはウィリアムズを拒絶するようになります。最後に彼女に言われた言葉で、ウィリアムズは胸を打たれ、今までとは違う働き方に目覚めます。
彼は答申を受け続けながら、無視し続けてきた貧困層が住む地域に公園を作る仕事に没頭し始めます。しかし、作品の中ではその仕事に向かうウィリアムズの背中を最後に、彼の死後の葬式の場面に移ります。
彼の葬式には、家族・同僚・議員、そして彼が公園づくりを成し遂げた貧困街に住む主婦たちが集います。そこでは、ウィリアムズの生前の行動が集った人々からポツリポツリと語られ、彼の命を懸けた行動とその功績が明らかになってきます。父の病気と行動を知らずにいた息子からは後悔が、生ける屍のように仕事をしてきた同僚からは賞賛と尊敬の念がふつふつと湧き上がってきます。
言葉ではなく行動でその功績を残し、関係した人々に利他の精神を宿したウィリアムズ。果たしてその利他的な行動は彼らと街を変えていくのか。ウィリアムズはたった一人の同僚に「それはすぐに忘れ去られてしまう」という言葉を手紙で残し、静かに去っていくのでした。
生きる LIVING ―― 撮影と編集について

黒澤作品にとても大きなリスペクトをはらった作品です。ストーリーにも撮影と編集にもそれが垣間見られます。オリジナルとは違いモノクロ撮影ではありませんが、画面には黒色の被写体が効果的に使われ、作品全体に「死」を感じる重苦しい空気感が漂っています。カラー映画であるからこそ、死の重苦しさと生の鮮やかさのコントラストが際立つ編集でもありました。
ただ、やっぱりオリジナルの黒澤映画の方がグっときたかな : )






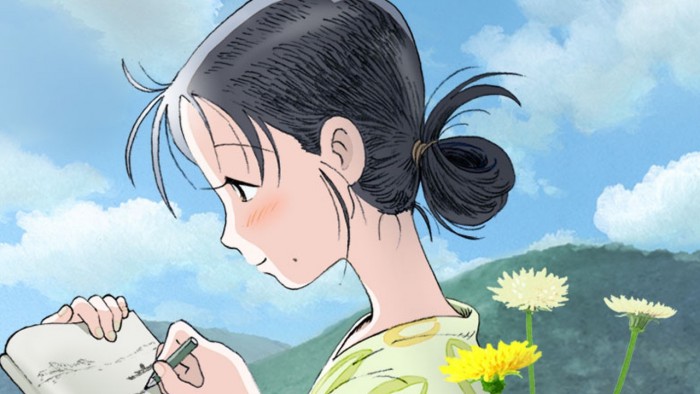






コメント - comments -